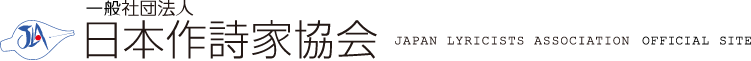2024年度事業報告 (自2024年4月1日~至2025年3月31日)
概 要
従来からの各事業については、会員の協力のもと確実に実施した。
2024年度も、「作詩の普及活動」として、9月2日から12月2日の3か月間「通信作詩講座(演歌・歌謡曲・ポップス)」を実施した。
同様に、2020年度から実施して高い評価を受けている公益的な文化事業「第4回作詩塾・ 東京【作詩講座2024】」を9月に開催した。
また、2019年4月の研修旅行会を最後に実施していなかった会員研修を、2025年2月20日「日本作詩家協会シンポジウム昭和歌謡を歌い継ぐ―美空ひばり」として開催した。
会員との懇談については、新型コロナウイルスの影響で中止していた総会後の懇親会を5年ぶりに開催した。
一方、著作権に関する諸問題等について、JASRAC及び他の関連団体と連携・協力しながら取り組んだ。
SNSを使った情報発信等については、2022年度から実施している協会の公式x(旧Twitter)で継続的に情報を発信している。
*会員異動状況
| 2024年4月 1日 | 800名 |
| 2025年3月31日 | 707名 |
| 入会者 | 20名 |
| 退会者 | 92名 |
| 資格喪失 | 10名 |
| 物故者 | 11名 |
(1) 年間事業
以下に記載する事業は、当協会が年間を通して行う継続事業である。
1. 第57回日本作詩大賞及び新人賞 (石原信一作詩大賞委員長)
「日本作詩大賞」は、協会が総力を結集して行う最大事業であり、音楽業界をとりまく厳しい環境の中で、音楽文化の発展に多大な貢献を果たしている。
第57回目を迎えた今回は、テレビ東京の支援のもと2024年12月7日(土)にBSテレ東で生放送された。その番組内で最優秀新人賞と優秀新人賞、そして佳作も発表された。
2024年度の作詩大賞候補は、レコード会社12社から48作品の応募があった。2024年度も、第1次選考を外部音楽ジャーナリストに委託し、第2次選考会をテレビ東京で行い、12月7日の本選に臨んだ。
新人賞は、新人作詩家の登竜門として音楽業界からも注目を集めており、最優秀作品と優秀作品はCD化され、入選作品を掲載した作品集を刊行した。作品集は入選者に贈呈し、一般には実費で頒布している。
今年度の新人賞は1300編の応募作品があり、第1次、第2次そして最終選考による厳正なる審査の結果、入選作品として109編が選ばれた。
その中から最優秀新人賞1編、優秀新人賞1編、佳作10編が決定した。
☆作詩大賞ノミネート15作品(タイトル五十音順)
| 「いのちの砂時計」 | 田久保 真見 |
| 「女がつらい」 | 麻 こよみ |
| 「紅の蝶」 | 松井 五郎 |
| 「恋…情念」 | 原 文彦 |
| 「こしの都」 | 合田 道人 |
| 「さらば桜島」 | 石原 信一 |
| 「三陸挽歌」 | たきの えいじ |
| 「庄内しぐれ酒」 | 荒木 とよひさ |
| 「白い花飾って」 | 星川 裕二 |
| 「TATSUYA」 | 吉田 旺 |
| 「涙唄」 | 水木 れいじ |
| 「涙ひとしずく」 | 酒井 一圭 |
| 「みだれ咲き」 | 木村 竜蔵 |
| 「迷宮のマリア」 | 松井 五郎 |
| 「夢みた果実」 | 幸 耕平 |
☆本選審査員(五十音順)
| 委 員 | 植木 理恵(心理学者) |
| 齋藤 孝 (教育学者) | |
| 高畑 淳子(女優) | |
| 武井 壮 (タレント) | |
| 立川 志らく(落語家) | |
| やすみりえ(川柳作家) | |
| ルース・マリー・ジャーマン(実業家) |
☆受賞作品
| 日本作詩大賞 | 「TATSUYA」 |
| 作詩 吉田 旺 | |
| 作曲 杉本 眞人 | |
| 編曲 川村 栄二 | |
| 歌唱 田中 あいみ | |
| 制作 日本クラウン株式会社 |
| 審査員特別賞 | 「こしの都」 |
| 作詩 合田 道人 | |
| 作曲 五木 ひろし | |
| 編曲 若草 恵 | |
| 歌唱 五木 ひろし | |
| 制作 株式会社ファイブズエンタテインメント |
☆新人賞授賞作品
| 最優秀新人賞 | 「月うるる」 |
| 作詩 榛澤 洋子 | |
| 作曲 徳久 広司 | |
| 編曲 猪股 義周 | |
| 歌唱 北山 たけし | |
| 制作 株式会社テイチクエンタテインメント |
| 優秀新人賞 | 「夢追い鶴」 |
| 作詩 砂川 風子 | |
| 作曲 徳久 広司 | |
| 編曲 猪股 義周 | |
| 歌唱 北山 たけし | |
| 制作 株式会社テイチクエンタテインメント |
| 佳作(10編) タイトル五十音順 |
「一寸先は…」 | 沙木 実里 |
| 「寛美一代」 | 吉岡 広己 | |
| 「九頭竜川」 | 水越 桂 | |
| 「玄界灘」 | 村田 文教 | |
| 「最北漁場」 | ふくし ゆうや | |
| 「聖徳太子の壱万円」 | 注連木 暁 | |
| 「たけしのデッカンショ」 | 大野 佑起 | |
| 「星くずの街」 | 安井 幸雄 | |
| 「港の赤トンボ」 | 遙 北斗 | |
| 「羅臼の |
こうしゅうち 憲 |
2. 「通信作詩講座(演歌・歌謡曲・ポップス)」 (髙畠じゅん子作詩講座委員長)
2024年度は、課題メロディーを委嘱しメロ先(曲先)の講座を新たに設けた。
また、第1期から第7期までの優秀作品13編は、日本作詩大賞新人賞入選作品と併せて、講評抜粋とともに作品集に掲載した。
第8期 2024年9月2日~2024年12月2日 受講作品数215作品
登録受講者数254名 うち会員41名
3. 「第4回作詩塾・東京 作詩講座2024」 (髙畠じゅん子作詩講座委員長)
「講師と参加者の方々が“詩”について語り合えるような“少人数での勉強会”」を趣旨として参加者を会員、一般から公募し、38名の参加者を8グループに分けてそれぞれに理事が講師として参加した。参加者各自1編の作品を持ち寄ってテキストとし、講師による講評や参加者同士の合評を行った。
当初予定した8月31日、9月1日は、台風による暴風雨や交通機関不通のため実施を見合わせたが、受講者の強い要望や講師の熱意により、全参加者への連絡・調整、グループ分け変更、参加不能者への返金等振替作業を行った結果、協会事務所において2024年9月20日から9月29日のうち8日間、1日1グループずつ実施した。
参加者からは、「作詩するにあたって日常の感性やアンテナを張ることの大切さ、言葉の伝え方など学ぶことが沢山あり役に立った。」等の高い評価を受けた。
4. 2024年版 年刊詩謡集「きょうの詩 あしたの詩」 (たきのえいじ詩謡集委員長)
本事業の主な目的は「作詩の普及」で、作詩家協会の会員が新人からベテランまで、この一冊のために一編だけの新作を持ち寄って作りあげる作品集である。これだけの作品集を出し続けている団体は作詩家協会だけで、会員の喜びと誇りが詰まっている。
歴代会長・委員長の序文はこのことを味わいのある言葉で書かれているので、是非ともご一読いただくことをお勧めしたい。
参加作品は143編であった。
なお、2022年度から、著作権保護の観点から当協会のホームページ上への掲載は、装丁、序、作品タイトルのみに変更した
5. 会報・協会ホームページ (久仁京介広報委員長)
実務報告を加え、執行部と会員、または会員相互の交流を図ると同時に、関係団体とコミュニケーションの円滑化をはかるものである。
- 年4回 4月,7月,10月,12月発行(No. 227~230) 発行部数 900部
ホームページは、会員サービスの一層の充実をはかると共に、情報開示が求められており、当協会もオフィシャルホームページで一般にも情報発信をしている。
ホームページでは、当協会の紹介、日本作詩大賞及び新人賞、作詩家協会作詩講座、ソングコンテストグランプリ、作品集、入会案内などを掲載している。
6. 研修会 (万城たかし研修委員長)
旅行に限ることなく会員のための研修を行う観点から2024年度は、「日本作詩家協会シンポジウム昭和歌謡を歌い継ぐ-美空ひばり」として未来に歌い継ぐべき昭和歌謡を作詩家協会の視点で取り上げた。
時代の中で燦然と輝いた昭和歌謡は、令和の今、YouTubeやサブスクリプション配信等で再び脚光を浴びつつある。年代を超えて歌われはじめた昭和歌謡を、再度クローズアップしようと考えた今回のシンポジウムは、特に昭和の歌謡史に輝かしい女王の名を刻む美空ひばりさんを、その歌から、その生き様から多角的に分析しようと試みた。ご子息の加藤和也さん、ゲスト歌手としてテレビ朝日の博士ちゃんシリーズで美空ひばり博士となった梅谷心愛さんを招き、貴重な音源や映像を交えてトークと歌で足跡を追った。
マスコミからは「実際のSP盤やEP盤からの歌声や、貴重な当時の写真や映像も豊富に使用しながらのトークが展開され、美空ひばりというスーパースターの、そして彼女の歌の魅力をわかりやすく伝えてくれたと言えよう。」等の評価を得た。
7. 日本作曲家協会との共同企画 作詩・作曲コンテスト「ソングコンテストグランプリ・2024」
(石原信一ソングコンテスト委員長)
2024年度の作詩部門の募集は2024年1月15日~3月15日、歌唱は走裕介(日本コロムビア)で応募作品は、1189編となった。
最優秀作詩賞には、「孤狼 よ走れ」(広瀬ゆたか)、「男が母を想う時」(佐藤勝美)」の2編が選ばれ、他に優秀作詩賞2編、佳作9編が入選した。
2025年度も日本作曲家協会との共同企画で行うこととし、歌唱は松原のぶえ(徳間ジャパンコミュニケーションズ)に決定した。応募窓口は日本作曲家協会で、作詩募集期間は、2025年1月15日~3月14日、応募作品は816編で最優秀作詩賞2編を課題詩に、4月21日~6月20日作曲部門が募集された。
8. 情報発信等のIT化 (松井五郎マルチメディア委員長)
SNS(ソーシャルネットワークサービス)を利用した情報発信の方法として、2022年10月26日から協会の公式x(旧Twitter)を開始した。作詩大賞新人賞やソングコンテストグランプリ等の作品募集や協会の事業などを発信し続けている。スピーディーでバラエティー豊かな情報発信を目指している。
9. 財務委員会 (原文彦財務委員長)
協会事業の予算・決算に関する企画立案を行った。
(2) 協賛事業
主な関係団体への協賛
- JASRAC賞の贈呈式及びJASRAC主催の各文化事業(日本音楽著作権協会)
- FCA(一般社団法人日本音楽作家団体協議会)アンケート「音楽作家の実態・意識把握調査」
- 日本作曲家協会の音楽祭(日本作曲家協会)
(3) その他の実施事項
1. 理事会
理事会は、原則月1回開催される。
協会の事業遂行に関する事項について決定し、事業計画及び収支予算、事業報告及び決算等々を検討、社員総会において審議・決議、報告していくものである。
2. 社員総会
事業報告及び決算、事業計画及び収支予算等々の諸問題を審議し決議する。
- 6月28日(金)ホテル ルポール麹町
議案 1. 2023年度事業報告について
2. 2023年度決算報告について
3. 2024年度事業計画について
4. 2024年度収支予算について
5. 理事16名選任について
6. 監事 3名選任について
7. 会費改定について
3. 委員会
各委員会は、理事会で決定した事項によりその実務を遂行している。
60周年事業委員会、作詩大賞委員会(新人賞選考委員会含む)、 作詩講座委員会(通信作詩講座、作詩塾)、ソングコンテスト委員会、 詩謡集委員会、広報委員会(会報、ホームページ)、研修委員会、 財務委員会、マルチメディア委員会
4. 全国地区会
各全国地区会の自主的活動を第一としており、地方の会員が自主的に勉強会や懇親会を各地区で開き、その場所に会員の要望で役員が出張して親睦を深める等、各地区の充実と発展を主たる活動方針に揚げている。
全国地区会は、北海道、東北、北関東(茨城・栃木・群馬)、埼玉、千葉、東東京(世田谷・杉並・練馬区を除く区部)、西東京(世田谷・杉並・練馬区・市部)、神奈川、北陸甲信越、東海、近畿、大阪、中国、四国、九州・沖縄の15地区会となっている。
2024年度4月期決算報告書(PDF:204KB) 
以上